〜人生後半戦を豊かにする読書体験〜
はじめに
実は40代になるまでは小説大好きっこでした。サブスクで映画やドラマを見始めるまでは、週1冊は最低でも読んでました。フィクションばっかりでしたけどね。40代後半になり、読書タイムがリラックスタイムに繋がるという理由で読書再開しました。今は実用書ばかり読んでます。好みって変わりますね。でも守備範囲は広いほうだといえますよね。これからも、自分の興味の向くまま、ジャンルを問わず本を手に取っていくつもりです。
今回は最近読んだ7冊の中から、特に印象深かった作品をご紹介します。ビジネス書からエッセイ、健康本、SF入門書まで、一見バラバラに見えるラインナップですが、どれも40代の私の心に深く響いた一冊たちです。
読書は人それぞれの体験ですが、同世代の方々の本選びの参考になれば幸いです。
1. エッセンシャル思考 – グレッグ・マキューン
本の概要
副題:最少の時間で成果を最大にする
著者:グレッグ・マキューン(翻訳:高橋璃子)
出版社:かんき出版
ページ数:320ページ
概要
現代社会において「何でもできる」という幻想に惑わされがちな私たちに、「より少なく、しかしより良く」という生き方を提案する書籍。エッセンシャル思考とは、「本当に重要なことを見極め、それ以外は思い切って捨てる」考え方のこと。
主要なテーマ
- 選択の力:自分で選ぶことの重要性
- ノイズの除去:本質的でないことを見極める技術
- トレードオフ:何かを得るために何かを諦める覚悟
- エッセンシャル思考の実践方法
こんな人におすすめ
- 仕事に追われて自分の時間がない人
- やることが多すぎて優先順位がつけられない人
- 40代以降で人生を見直したいと考えている人
- 管理職として部下のマネジメントに悩んでいる人
感想
ちょっと完璧主義なところがありまして私。なんでもかんでもやっちゃうというか、やりたがっちゃうんです。さすがにアラフィフともなると、背負うのが辛くなってきました。身軽になりたい。リリースしたい。そう思った時に出会えた本です。大事なことをやるだめには、大事じゃないことをしない。シンプルだけど難しい。でも人生は選択の連続です。肝に銘じて読みましたよ。
2. ランチェスター戦略 「弱者逆転」の法則 – 福永雅文
本の概要
副題:小さくても勝てる企業になる
著者:福永雅文
出版社:日本実業出版社
ページ数:240ページ
概要
第一次世界大戦時にイギリスの航空工学者ランチェスターが発見した法則を、現代のビジネス戦略に応用した実践的な戦略論。「強者の戦略」と「弱者の戦略」を明確に区別し、自分たちの立ち位置を正しく把握することから始まる戦略思考を説く。
主要なテーマ
- 強者と弱者の戦略の違い
- 局地戦の重要性:狭い分野で1位を目指す
- 接近戦と差別化:競合との戦い方
- 一点集中の法則:経営資源の集中投入
- 市場シェアと収益性の関係
ビジネス以外への応用
- 個人のキャリア戦略
- 副業や転職での競争戦略
- 人生設計における選択と集中
こんな人におすすめ
- 中小企業の経営者・管理職
- 大企業の中でも「弱者」の立場にいる人
- 副業や独立を考えている人
- 競争の激しい業界で働いている人
感想
零細企業の舵取りをしている身としては、即戦力となるような戦略本でした。発想の転換ともいいますが、弱者がどう強者と戦うか。商売のチャンスやひらめきが転がってました。身近な企業での例なんかもわかりやすかったし、戦国時代や実際の戦闘でのたとえもわかりやすかったです。戦う企画戦略マンには必読書でしょうけ。
3. ファスト教養 – レジー
本の概要
副題:10分で答えが欲しい人たち
著者:レジー
出版社:集英社新書
ページ数:256ページ
概要
現代社会における「教養」の在り方を鋭く分析した話題の書。SNS時代において、複雑な物事を短時間で理解したがる「ファスト教養」の風潮を批判的に検証しながら、本当の教養とは何かを問い直す。YouTubeやSNSで情報を得ることの功罪、そして深く考えることの価値を説く。
主要なテーマ
- ファスト教養の正体:即効性を求める現代人の心理
- SNSと教養:情報の断片化がもたらす影響
- 本当の教養とは:時間をかけて身につけるものの価値
- メディアリテラシー:情報を見極める力
- 知的好奇心の育て方
著者について
TwitterやYouTubeで社会問題について発信している論客。政治、社会、文化について独自の視点で切り込む発言で注目を集めている。
こんな人におすすめ
- SNSで情報収集することが多い人
- 「すぐに答えが欲しい」と思いがちな人
- 現代の情報社会に違和感を感じている人
- 本当の教養を身につけたいと考えている人
感想
ここで崇められている著名人が、まあそこらへんであることを踏まえるとわかりみが深い。一時代を築いたパネラー的な人たち。みんな彼らみたいな「教養」を持ちたいのだろうか? と思いながら拝読。まあ、そういう視点もあるのだろうなと勉強になりました。
4. 腸がすべて – フランク・ラポルト=アダムスキー
本の概要
副題:世界中で話題!アダムスキー式腸活メソッド
著者:フランク・ラポルト=アダムスキー(翻訳:森敦子)
出版社:サンマーク出版
ページ数:280ページ
概要
ヨーロッパで30年以上にわたって消化器系の研究を続けてきた著者が提唱する、革新的な腸活メソッド。従来の腸活とは異なり、食べ物を「ファスト」(消化の早い食品)と「スロー」(消化の遅い食品)に分類し、それらを同時に摂取しないことで腸の負担を軽減する方法を説く。
主要なテーマ
- アダムスキー式腸活の基本理論
- ファスト食品とスロー食品の分類
- 食べ合わせのルール
- 腸の汚れが引き起こす様々な症状
- 腸をきれいにする具体的な方法
- 腸と脳の関係:腸内環境がメンタルに与える影響
実践的な内容
- 食品分類表
- 1日の食事例
- 腸活に効果的な運動
- ストレス管理と腸の関係
こんな人におすすめ
- 慢性的な体調不良に悩んでいる人
- 従来のダイエットで効果が出なかった人
- 40代以降で代謝の低下を感じている人
- 腸活に興味があるが何から始めればいいか分からない人
感想
時代は腸活だよ。とか言いたくて読んだ。というのら嘘だけど、興味はあった。なんつったって第二の脳? 1番長い臓器。腸にいいエサ与えてこそ健康たもてる、みたいな。学びには充分すぎる、内容でした。結局早食いやめよう!って思ったはずなのに…。
5. SF超入門 – 冬木糸一
本の概要
副題:サイエンス・フィクションを読むには
著者:冬木糸一
出版社:筑摩書房(ちくまプリマー新書)
ページ数:192ページ
概要
「SFは難しそう」「どこから読めばいいか分からない」という人のために、SF小説の魅力と読み方を分かりやすく解説した入門書。SFの歴史、主要なテーマ、代表的な作家と作品を体系的に紹介しながら、SF的思考法の面白さを伝える。単なる作品紹介にとどまらず、SFが描く未来社会への洞察も含んでいる。
主要なテーマ
- SFとは何か:ジャンルの定義と特徴
- SFの歴史:黎明期から現代まで
- 主要なSFテーマ:
- タイムトラベル
- 宇宙開発・異星人
- AI・ロボット
- ディストピア・ユートピア
- サイバーパンク
- 日本SF界の特徴と代表作家
- SF映画との関係
紹介されている代表的作家・作品
- アイザック・アシモフ『ファウンデーション』シリーズ
- フィリップ・K・ディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』
- 小松左京『日本沈没』
- 筒井康隆の諸作品
こんな人におすすめ
- SF小説を読んでみたいが何から始めればいいか分からない人
- SF映画は好きだが小説は読んだことがない人
- 40代になって新しいジャンルに挑戦したい人
- 想像力を刺激する読書体験を求めている人
感想
SF苦手分野と得意分野真っ二つなんですけど、どんなのが面白いかなー?って思って読んでみたら、気になるのがたくさんありました。タイムトラベル時間系好きですが、宇宙系も面白そうでした。未知の分野もあって、今度読みたい積読リスト入りさせました。こういうキュレーション的な読本もいいですね!
6. カミーノ! 女ひとりスペイン巡礼、900キロ徒歩の旅 – もりともこ
本の概要
著者:もりともこ
出版社:新潮社
ページ数:256ページ
概要
スペイン北部を横断する巡礼路「カミーノ・デ・サンティアゴ」を、一人の日本人女性が35日間かけて歩き通した体験記。フランス国境の小村サン・ジャン・ピエ・ド・ポーから、最終目的地サンティアゴ・デ・コンポステーラまでの約900キロを、重いバックパックを背負って歩く日々を描く。
主要な内容
- 巡礼を決意したきっかけと準備
- 出発前の不安と期待
- 道中での出会い:世界各国からの巡礼者たち
- スペインの美しい風景と厳しい自然
- 体力的・精神的な限界との向き合い方
- 巡礼宿(アルベルゲ)での共同生活
- 言葉の壁を超えた人間同士のつながり
- 巡礼を通じて得た気づきと変化
著者について
イラストレーター・漫画家。日常を描いたエッセイ漫画で人気を博している。本書は文章のみで書かれているが、著者の温かい人柄と観察眼が随所に表れている。
巡礼路について
カミーノ・デ・サンティアゴは、9世紀から続く巡礼路で、1993年にユネスコ世界遺産に登録されている。現代では宗教的な意味だけでなく、自分自身と向き合う旅として多くの人に愛されている。
こんな人におすすめ
- 一人旅に興味がある人
- 人生の転機に立っている人
- 歩くことの意味を考えたい人
- 異文化交流に関心がある人
- 自分自身と向き合う時間を求めている人
感想
いつかは聖地巡礼したいなと思った。嘘じゃなくて本当に。面白おかしくライトなタッチで綴る、旅エッセイって感じでした。巡礼。距離的なことを考えると若いうちにチャレンジしたほうがいいのかな。この作品読了後、巡礼にまつわる映画も立て続けに見たのでかなり影響受けてます。
7. 怠けてるのではなく、充電中です – ダンシングスネイル
本の概要
著者:ダンシングスネイル(翻訳:吉川南)
出版社:KADOKAWA
ページ数:128ページ
概要
韓国で大ベストセラーとなった心の癒し系エッセイの日本語版。現代社会で疲れ切った心を持つ人々に向けて、「頑張りすぎなくていい」「完璧でなくていい」「今の自分を受け入れよう」というメッセージを、温かいイラストと共に届ける。短い文章で構成されているため、疲れた時にも読みやすい作りになっている。
主要なテーマ
- 自分を責めることをやめる
- 他人と比較することの無意味さ
- 休むことの大切さ
- 不完全な自分を愛すること
- 小さな幸せに気づく感性
- 現代社会のプレッシャーからの解放
- マイペースで生きることの価値
本書の特徴
- 見開き2ページで一つのメッセージが完結
- 韓国らしい温かいイラスト付き
- 心に響く短いフレーズが多数
- 疲れた時にぱらぱらと開いて読める構成
著者について
韓国のイラストレーター・エッセイスト。SNSで発信していた心に寄り添うメッセージが話題となり、書籍化に至った。「ダンシングスネイル」は「踊るカタツムリ」という意味で、ゆっくりでも自分らしく歩んでいこうという著者の人生哲学を表している。
こんな人におすすめ
- 仕事や人間関係に疲れている人
- 完璧主義で自分を追い込んでしまう人
- 他人と比較して落ち込みがちな人
- 心の癒しを求めている人
- 短時間で読める本を探している人
- 韓国文化に興味がある人
感想
そんなに大変か、韓国女子よ!というのは大げさかもしれない。国籍も性別もないかな。生きていくのって辛いじゃない。一生懸命って大変じゃない。いいのよゆっくりでさ。っていう小さな共感の連続をかわいらしい絵とともに綴ってくれていて、だれかには必要とされるであろう言葉たちが、ここにありました。
読書ログを始める理由
40代になって変わった読書への向き合い方
若い頃の読書
30-40代の頃は、主に日本の小説ばかりを読んでました。江戸川乱歩賞作家や大藪賞作家の本格的ミステリーから、純文学やほのぼのとした小説にいたるまで。呼吸をするかのごとく本当に毎日読んでましたし、仕事場へは2冊携帯していくのが常でした。フィクション好き男子だったわけです。
現在の読書スタイル
40代になって、サブスクで映画を見るようになってドラマにもハマってしまい、時を同じくして老眼デビューをして活字離れに拍車がかかりました。しかし、男性更年期で気持ちが落ち着かない時に、活字を目で追ってみたら「あれ? 落ち着く!」という発見がありました。それから、私は読書を再開させるにいたりました。
今後はブログで幅広い分野の読書をログを書いていければいいなと思ってます。
なぜ読書ログを書くのか
- 記憶の定着
読みっぱなしにせず、感想を言語化することで、本の内容がより深く心に残ります。 - 自分の変化の記録
どんな本に興味を持ったか、どんな感想を抱いたかを記録することで、自分自身の変化や成長を客観視できます。 - 同世代との共有
同じような人生ステージにいる方々と、読書体験を共有したいという思いがあります。 - 新しい本との出会い
読者の方からのおすすめ本情報をいただくことで、自分だけでは出会えなかった本に巡り会えることを期待しています。
まとめ
このブログでは、40代男性の視点から様々な本の感想をお伝えしていきます。専門的な書評ではなく、一読者として素直に感じたことを書いていくつもりです。
お願い
- おすすめの本があれば、ぜひコメントで教えてください
- 同じ本を読まれた方は、感想を共有していただけると嬉しいです
- 「この本についてもっと詳しく知りたい」というリクエストもお待ちしています
読書は本来、とても個人的な体験です。しかし、その体験を誰かと共有することで、さらに豊かなものになると信じています。このブログが、読書好きの皆さんの交流の場になれば幸いです。
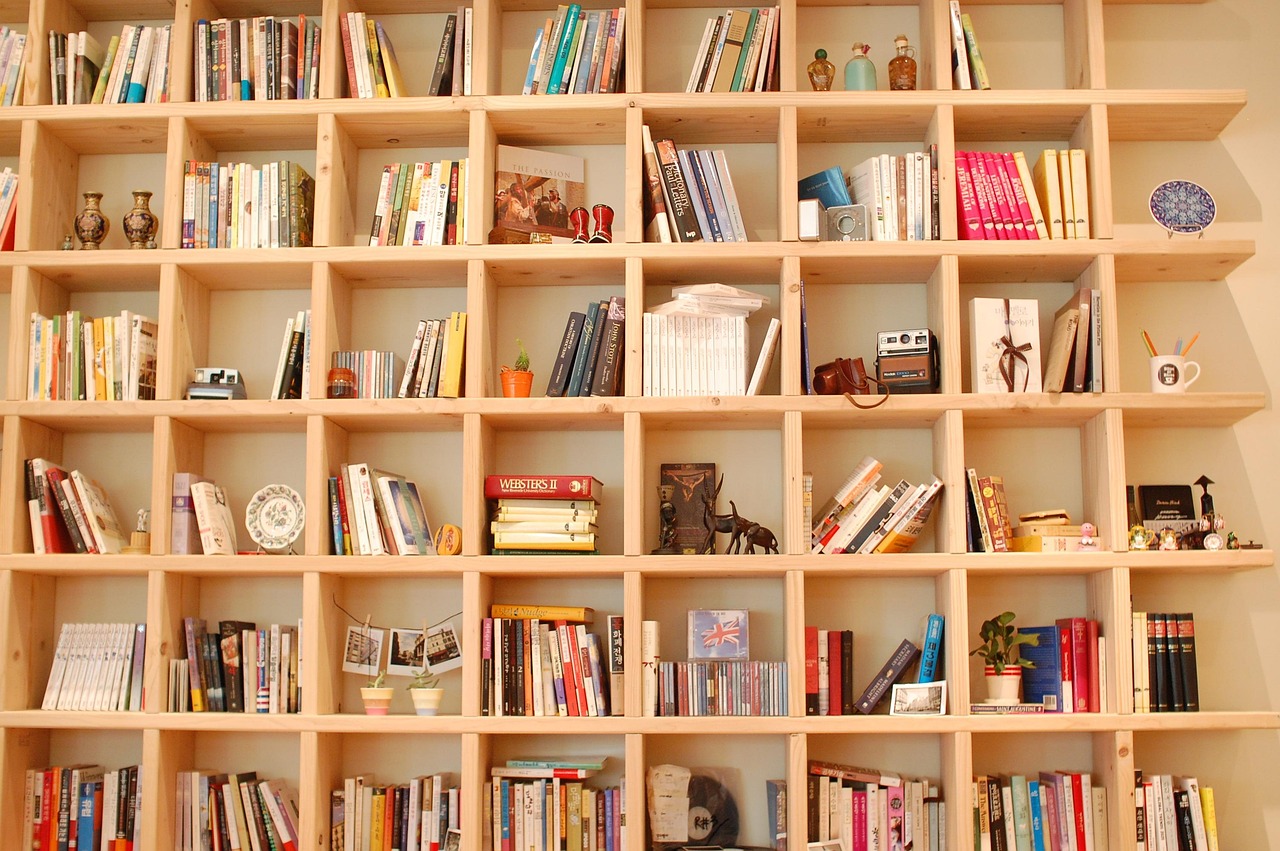


コメント